香川大学で開催された経営行動科学学会の第28回年次大会(2025年11月15日・16日)に出席し、組織行動や人事マネジメントに関する最新の研究成果を多数学んできました。
私の専門領域である人事・組織開発に関して、および、自身が2016年に独立、2018年に法人化(アルドーニ株式会社)したフリーランスとしての立場から、特に注目すべき重要テーマを抜粋します。
リーダーシップ研究
プロアクティブ行動の二面性
従業員の自発的な行動であるプロアクティブ行動には、「良い状態をさらに良くする促進型」と、「悪い状態を正しい状態に戻す問題予防型」という二つの側面があります。
変革型リーダーシップは、これら両方の行動を促すことが示されています。しかし、特に問題予防型プロアクティブ行動に対しては、その効果が直線的ではないという複雑な関係が見られます。上司のリーダーシップが中水準だと、部下は「支持されるか反発されるか」が不確実なため行動が抑制されます。一方で、高水準のリーダーシップは部下に安心感を与え、行動を促します。したがって、問題予防型の行動(周囲の反発を招きやすい性質を持つ)を組織内で促進するためには、上司の一貫した姿勢が鍵となります。
現場と人事・経営層の間で再確認された「リーダー期待のギャップ」
企業が求めるリーダー像について、人事や経営層は、組織変革やイノベーションを期待する傾向があります。一方、現場でミドルマネジャーの直属上司となるシニアマネジメント層は、「上位方針への協働と堅実な戦略実行」を重視しています。
このように、企業の人事責任者らが求める「変革志向」と、現場のシニアが求める「既存事業の堅実な推進」の間には、期待のギャップが存在することが再確認されました。これは、どちらが正しいという次元の話ではなく、「両利きの経営」の視点を持って、現場のマネジメントの中でどのように両立させるかという課題として捉える必要があります。
上司・部下研究
「使えない上司」に対する部下の複雑な戦略的反応
上司の行動が部下に与える影響は、上司の能力や特性だけでなく、部下自身の組織に対する姿勢(部下の特性)によって、非常に複雑に「調整」されます。
特に、組織に対して無関心な態度を貫きたい部下(自分の業務に「干渉されたくない」「邪魔されたくない」という理想を持つ)の反応は、上司の「使えなさ」のタイプによって明確に分かれます。
管理能力が欠けている上司への反応
このタイプの上司は、「無能ゆえに他者を巻き込む存在」として部下に認識されるため、結果的に部下に余分な負担(コスト)となります。長期的な関係をあきらめ、関わりを断とう(放棄しよう)という戦略的な判断が行われます。
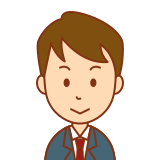
思い当たる節がある・・・
無気力でやる気がない上司への反応
このタイプの上司は、上司としての役割を放棄している状態であり、「何も指示を出さない非力な人」と見なされます。組織に無関心な部下にとって、「干渉されない、邪魔もされない」という理想を貫く上で、何も指示を出さない無気力な上司は最適な存在となります。
無気力な上司も、無関心な部下からは直接的な批判を受けないため、快適な上下関係を維持できます。その結果、両者の間には「お互いに干渉しない・干渉されない」という、一見すると平和ですが、健全ではない共存関係が生まれている可能性が推察されます。
このように、部下は、上司との関係を「自分への負担」や「得られる利益」を基準に評価し、許しや関係の放棄など多様な反応を選択していると考えられます。
フリーランス研究
2016年の独立以来、フリーランスとして活動を続けている(2018年に法人化)当事者であるため、今回の学会では、フリーランサーのキャリアを阻むもの・支えるものについての実証研究が報告されており、強い関心を持ちました。
従来、フリーランスという働き方で大きな課題と考えられていたのは、「生計を立てる上での経済的な困難(viability challenge)」、つまり「収入が不安定」「仕事が途切れたらどうしよう」というお金や生存に関わる不安でした。
しかし、今回の研究では、それ以上に「職業的アイデンティティに関わる困難(identity challenge)」という、自己認識や存在意義に関わる困難に注目しています。「アイデンティティ困難」とは、簡単に言うと、フリーランスであるがゆえに「働くプロフェッショナルとしての自分の姿や、仕事の役割を明確に定義できず、自己認識が揺らいでしまう状態」を指すようです。
フリーランサーが抱える「職業上のアイデンティティ(自己認識)が揺らぐ」という困難(負のプロセス)を乗り越えるのを助け、心の支え(心理的な保護資源)となるのが、その仕事に対する明確な「天職意識」(コーリング)です。そして、「この仕事は自分の天職だ」という意識が低い人ほど、アイデンティティが揺らぐことによって、キャリアの成功感や成長への期待が失われてしまう危険性(負の影響)が強まることが示されました。逆に言えば、天職意識が高いほど、フリーランス特有の困難に直面しても、キャリアのモチベーションが保たれやすいということです。
所感
実務上はどう転んでもこうだろうなということを仮説をたてて、統計学などを駆使して説を立証するというアカデミック全開な発表に驚いたり、感心する点もありました。「それを研究するの?」という内容もあり、おもしろかったです。今回の学会の研究成果は、日本企業が直面する「ミドルの役割変化」や「上司・部下関係の複雑化」が改めて可視化される内容でした。人事として、制度と運用のアップデートが求められると感じました。
基調講演をふまえて、丸亀町商店街のドーム(サムネ画像参照)がどんな経緯でできたのかを知ってから改めて見ると感慨深い。






